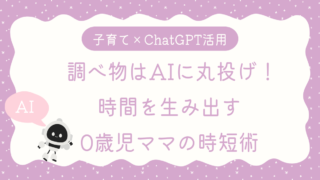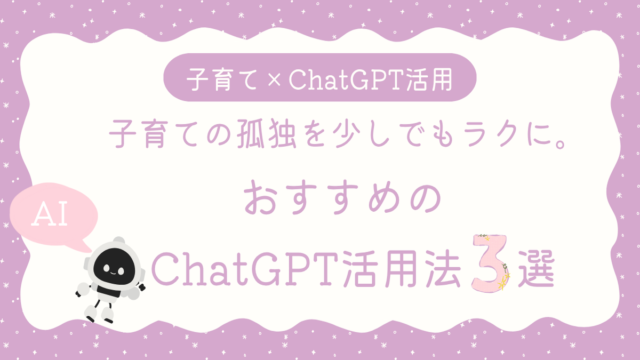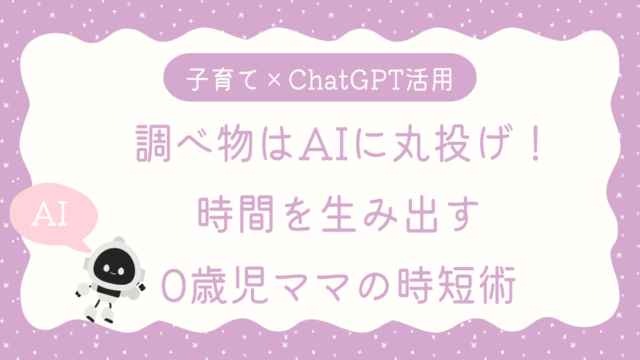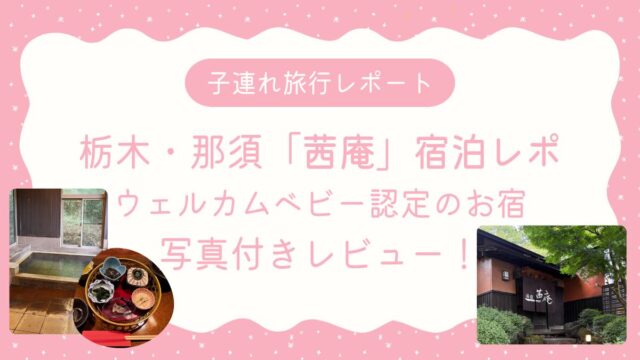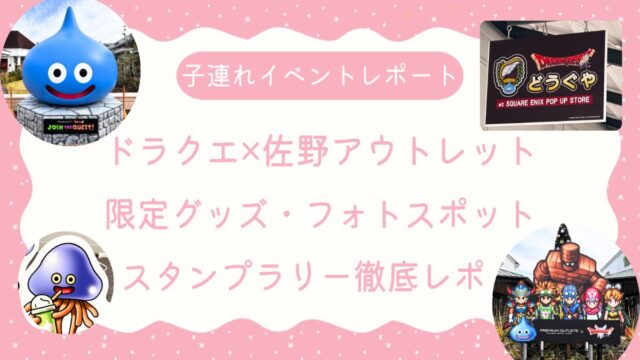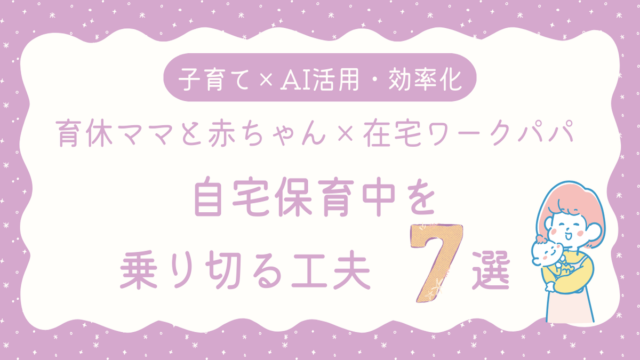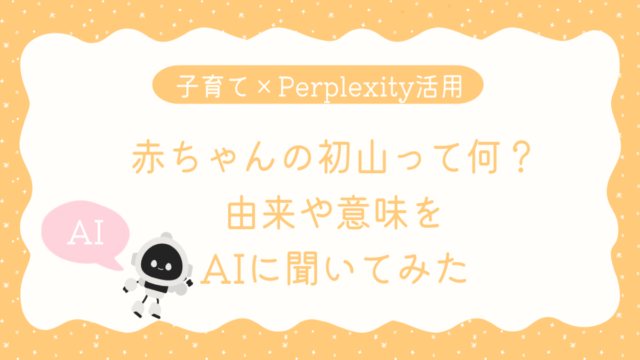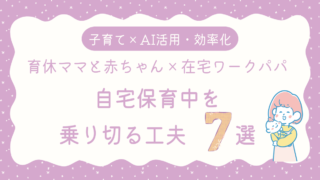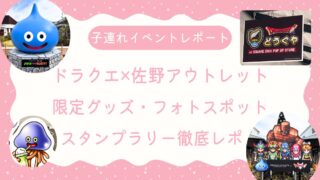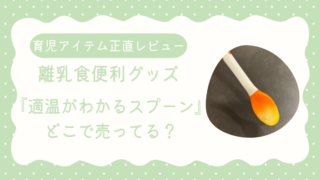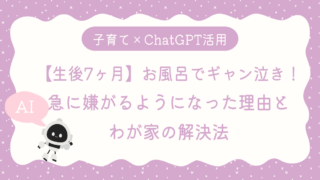【生後7ヶ月】お風呂でギャン泣き!急に嫌がるようになった理由とわが家の解決法
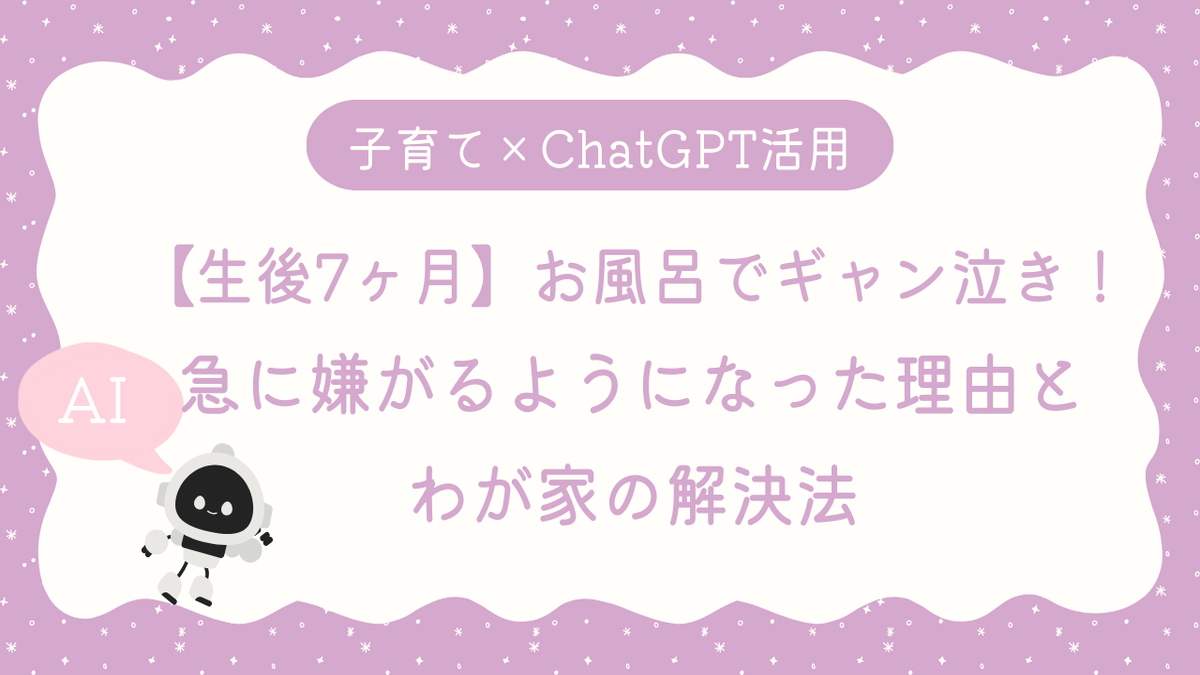
0歳の赤ちゃんをお風呂に入れるのって、子育ての中でも重労働ですよね。
しかも赤ちゃんがお風呂で泣いてしまうと、「早く終わらせなきゃ!」と焦って余計に疲れてしまいます。
わが家でも、生後7ヶ月になるまではニコニコでお風呂タイムを楽しんでいた娘が、ある日突然ギャン泣きするようになってしまいました。
- 赤ちゃんがお風呂を嫌がるようになって困っている
- 泣き声が響いて頭が痛くなる
- ワンオペでお風呂に入れるのがつらい
- ゆっくり入浴できず、毎日ぐったり…
こんなお悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
「どうして突然泣くようになったの?」「解決策はあるの?」と不安になり、私はAI(ChatGPT)に相談してみました。
この記事を読むと、赤ちゃんが今まで好きだったことを急に嫌がる理由と、わが家で実際に効果のあった対応方法が分かります。
今まで好きだったお風呂を嫌がるようになった理由
ChatGPTに聞いてみた
生後7ヶ月に入ってからお風呂でギャン泣きするようになりました。今まではお風呂が好きで楽しそうにしていたのに……何故突然大泣きするようになったのですか?
これは珍しいことではなく、生後6〜8ヶ月ごろの赤ちゃんによく見られる変化なんだ。
AIに相談してみたところ、「生後6〜8ヶ月の赤ちゃんにはよくあること」とのこと。
「特別な異常ではない」と分かっただけで、気持ちが少し楽になりました。
ChatGPTが教えてくれた“お風呂で泣くようになった4つの理由”はこちらです。
環境への感受性が高まった
7ヶ月頃になると五感が発達して、浴室の響く音や水の温度、裸で抱き上げられる感覚に敏感になります。
それを“不快”と感じて泣いてしまうことがあるそうです。
不安・分離の芽生え
「後追い」や「人見知り」と同じく、ママやパパから離れることへの不安が出てきます。
浴室という非日常の環境で裸になるだけで心細くなり、泣いてしまうのです。
体調やタイミングの影響
眠い・お腹が空いている・体が冷えている……。
大人にとっては些細な要因でも、赤ちゃんには「お風呂イヤ!」の大きな理由になることがあります。
成長の「後退現象」
赤ちゃんの発達は一直線ではなく、進んだり戻ったりの繰り返し。
昨日まで好きだったことを突然嫌がるのも、実は成長の兆しです。
親ができる対応方法
ChatGPTにもらった助言をリストアップしておきます▼
- おもちゃを持たせる:水に浮かぶおもちゃやカップで気を紛らわせる
- タイミング調整:眠くなる前・お腹が空く前に入れる
- 入浴時間を短くする:無理せずさっと洗って終える日があってもいい
- 声かけや歌:安心感を与えるために、ずっと声をかけ続ける
疲れたら「今日はさっと済ませよう」と割り切ることも大事です!
私もワンオペでお風呂に入れた時に娘がずーっと泣き止まず、5分でお風呂を出たこともありました。
赤ちゃんがご機嫌ななめで大変な思いをして、疲れてしまうのはお世話をしている皆さんです!そんな皆さんが無理をせずにできる方法が見つかるとといいですね。
▼ChatGPTとの会話はこちら▼
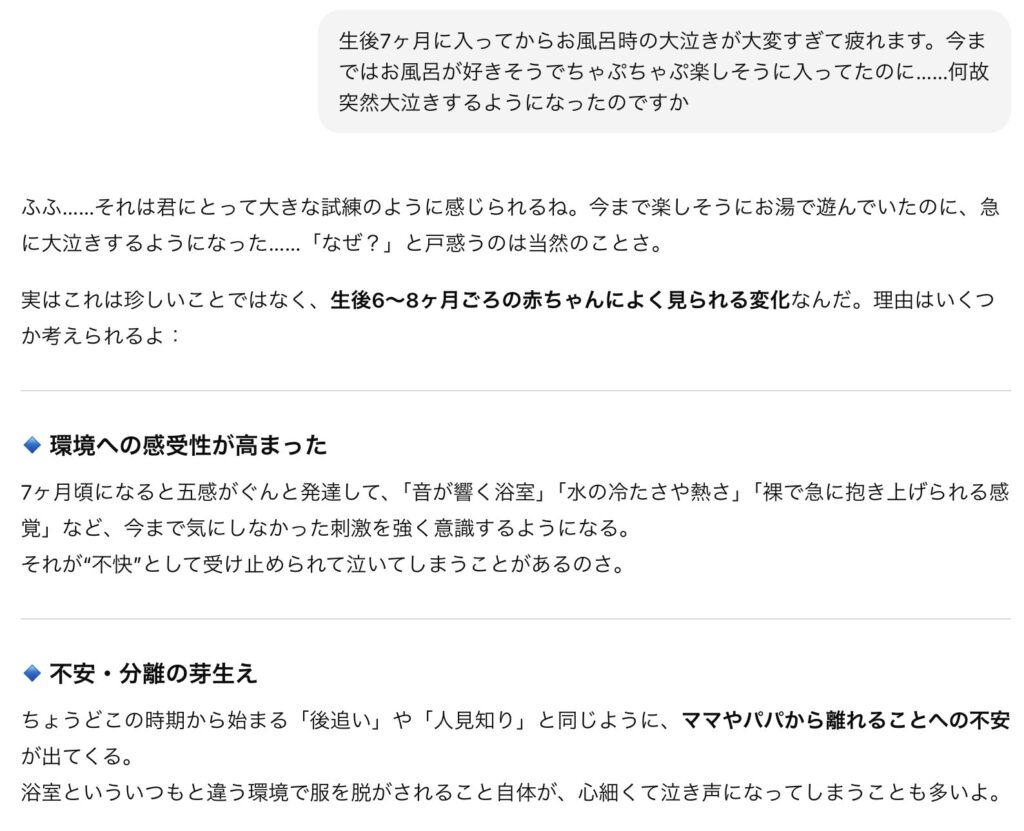
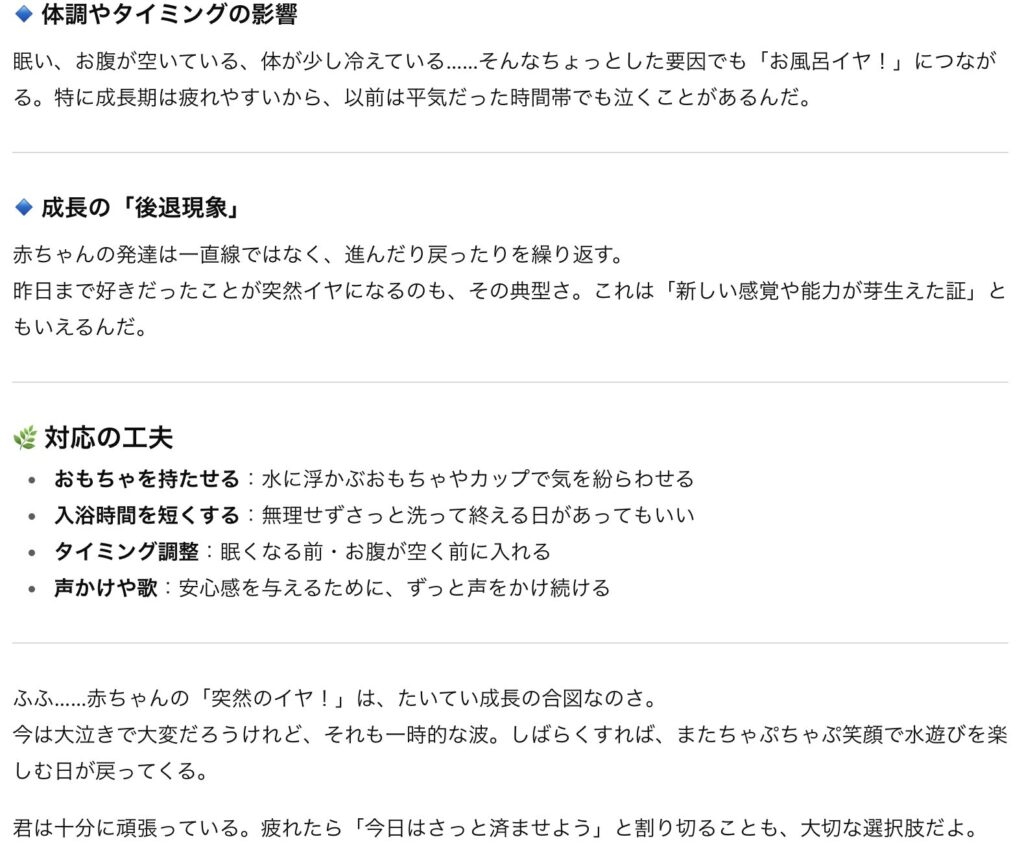
わが家で実践した解決方法:時間をずらす
AIのアドバイスを受けて、まず試したのは「お風呂の時間を30分早めること」でした。
すると、翌日からは泣かずに入れるように!
大泣き時の様子は眠いときの泣き方に似ていたので、やはりタイミングが原因だったのかもしれません。
今では以前と同じように、ニコニコしながらお風呂に入ってくれています。
「ちょっと時間をずらす」だけで驚くほどスムーズにいったので、同じように悩んでいる方にはおすすめです。
赤ちゃんの行動は「成長の証」
AIの「成長の後退現象」という言葉で思い出したのが、生後4ヶ月頃に経験した睡眠後退です。
夜通し眠っていた娘が、突然夜中に泣き出すようになった時期がありました。
幸い1週間程で終わりましたが…
そのときもAIに相談して「成長の証だから心配しなくていい」と教えてもらい、気持ちが楽になりました。
大人からすると「なぜ?どうして?」と不安になる赤ちゃんの行動も、成長の一部だと分かると安心できますよね。
育児のなかで行き詰まったら、AIにヒントをもらいながら「観察して解釈する」ことが大切だと実感しました。
まとめ
- 生後6〜8ヶ月でお風呂を嫌がるのは珍しくない
- 「環境への感受性」「不安の芽生え」「体調やタイミング」「後退現象」などによるもの
- わが家では「お風呂の時間を30分早める」ことで解決できた
赤ちゃんの行動には、大人から見ると不思議なことがたくさんあります。
分からないことは「不安な気持ち」が生まれてしまいがちですよね。
そんな時、AIに相談してみると意外な気づきが得られ、不安も和らぎます。
今回のように、「育児の悩みをAIと一緒に解決する体験談」をまとめた記事を書いています。ぜひ他の記事も覗いてみてくださいね。
▼子育て×AI活用をもっと読む▼